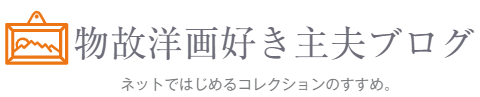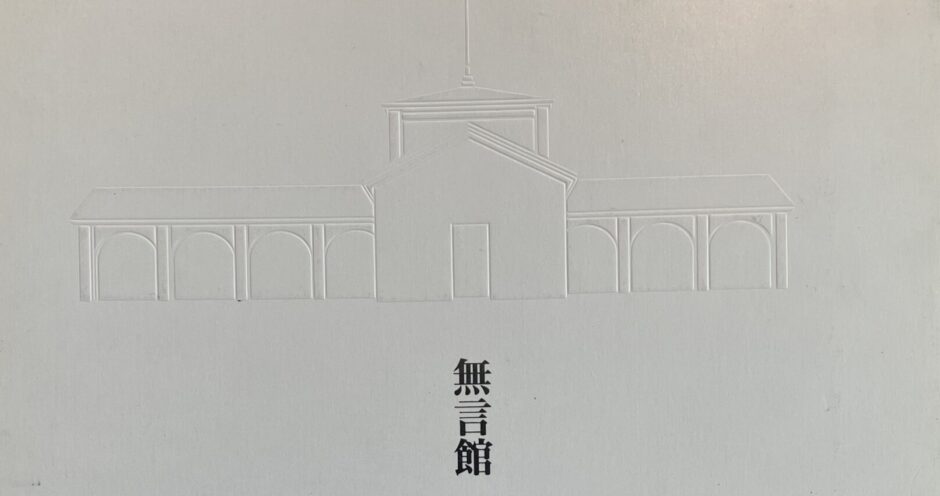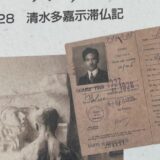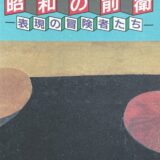こんにちは!
本日もよろしくお願いします!
1、第二次世界大戦の時代
今回おすすめしたい図録はこちら。
『無言館 遺された絵画展』(窪島誠一郎監修 NHKきんきメディアプラン 2005)

この図録は長野県上田市にある美術館「無言館」の図録です。無言館は戦没した画学生の遺作を集めて展示している美術館で、僕も行ってみたいと常々思っているのですが、残念ながらまだ行けていません。
今回、なぜこの図録を選んだのかというと、今まで図録をおすすめしたり、書籍やコレクションを解説する中で、皆様もおおよその日本洋画史の流れをつかめてきたのではないかと思います。
簡単にまとめると……
江戸の洋学から明治維新の産業目的での洋画の需要、工部美術学校の設立から明治美術会が誕生、黒田清輝らパリ留学第1世代による白馬会創立からの東京美術学校西洋画科の設置、そこから藤島武二などの助教授らが第2世代としてパリに留学します。その後は水彩画ブームが起き、日本水彩画会、国の展覧会である文展、白馬会の後進である光風会ができ、画家志望者が急増、東京美術学校の生徒たちを中心にたくさんの画家がパリに渡って絵を学びます。そこから帰国した第3世代たちが二科会やヒュウザン会、一九三〇年協会などで活躍を見せ黄金期を迎える。そこまではさらっとですが追えたと思っています。
そして、次に来るのがその彼らの子供たちの世代、1910年前後から1920年前後に生まれたものたちの話なのです。広本季与丸、木内廣もこの世代に当たります。千葉勝はこの二人より少し若いため、出撃を免れました。
つまり、彼らは生まれた時代故に否応なく兵士として戦争へと応召された世代で、そして日本洋画史においてはいつも避けて通られてしまう世代なのです。
しかし、ここまで曲がりなりにも流れを時代通りに追ってきて、ここを避けては物故画家に対して誠実ではないと僕は考えています。なので、今回はこの日本洋画史を分断するとされている時代の話を、この素晴らしい仕事をしている図録の力を借りてしていきたいと思います。
2、野見山暁治と窪島誠一郎
無言館を語る上で、まずは二人の人物に触れなければなりません。
一人目は画家の野見山暁治です。野見山は1920年生まれで現在なんと御年101歳!お元気でいらっしゃいます。東京芸術大学名誉教授であり、2014年に文化勲章を受章したのは記憶に新しいですよね。野見山はとても素晴らしいエッセイや本をたくさん書いていることで古本好きの間では有名です。また作家の田中小実昌の義理の兄であることも古本好きを嬉しがらせるポイントなのです。
と、話が脱線しそうになりましたが、1920年生まれの野見山は東京美術学校を卒業後、やはり戦争に応召され満州に向かいます。しかしそこで肺に水が溜まるなどして体調を崩し、仲間を残して帰国します。仲間からはうまくやったもんだ、羨ましいと、そんなことを言われたそうです。その帰りの列車の中から見えた野営地の光が未だに忘れられないと野見山は語ります。確かにそうだ、と。とにかく生きて帰れる俺は絵が描けるんだから。みんな絵が描きたくて仕方ないんだ。でも、死んだらもう絵は描けない。
その後、日本に帰った野見山の病気はあっさり治り、戦争も終わった。一方、生きて帰れなかった仲間たち、死んでしまった学校の先輩や後輩たち。
その思いがずっと心に残っていたのか野見山は三十年後、戦没した学校の同級生や先輩後輩の遺族を訪ね歩き、遺された作品を一冊の画集にして『祈りの画集 戦没画学生の記録』野見山暁治・宗左近・安田武 著 小野成視 撮影(日本放送出版協会 1977)を出版します。
この『祈りの画集』を読んだ窪島誠一郎と野見山がさらに約二十年後に出会い、無言館設立へと話が進むのですが、その前に窪島についても触れていきたいと思います。
窪島といえば一般的には実父が作家の水上勉だったことが発覚し、一躍時の人となったことが有名だと思いますが、物故洋画コレクターとしてはかつて明大前駅にあったという「キッド・アイラック・アートホール」というギャラリーを経営していた人という方が真っ先に頭に浮かびます。というのも、いのは画廊にいらっしゃる常連さんはだいたい、窪島の「キッド・アイラック・アートホール」か、洲之内徹の「現代画廊」か、梅野隆の「美術研究藝林」のいずれか、もしくは複数の常連だった人たちなので、たまにそれぞれの画廊主の話が出るのです。
窪島はギャラリーを経営しながら、村山槐多や関根正二、靉光、松本竣介といった夭折画家のデッサンを収集していました。そしてそれらを展示する美術館「信濃デッサン館」を長野県上田市に建設します。
そんな時に野見山と窪島は出会い、『祈りの画集』の話をするのですが、語りながら遠くを見るような目をする野見山の気持ち、その目の意味を推し量れない自分の浅い戦争理解を窪島は悟ります。そして、美術館を作りたかったと漏らす野見山に思わず「やりましょう。手伝います」と言ってしまうのです。
そんな二人がタッグを組み、野見山のかつて訪ねた遺族の元を巡るのですが、その話は『「無言館」への旅 戦没画学生巡礼記』窪島誠一郎(小沢書店 1997)に詳しいので是非読んでみてください。
3、積み残されたもの
自称貧乏ギャラリストの窪島が、すでにひとつ美術館を経営しているにも関わらず、もうひとつ美術館を建てようなんて無茶にも見えるのですが、運よく支援者が見つかり現在に至ります。そして、この窪島の成し遂げた仕事は思いの外、美術愛好家からあまり大きな反響を得られずにいます。
これは支援者探しをしていた当初から言われていたことらしいのですが「無名の学生の絵なんて飾って何になるんだ」とか、「心がけは殊勝だけど見に来る人なんているのかね」だとか、とにかく首を傾げられたそうです。
当然、飾られている絵はどれも学生時代の絵か、卒業後まもない頃の絵です。中にはその頃から才能を確かに発揮している絵もあるのですが、そうでない発展途上の絵もたくさんあります。しかし、それは当たり前なのです。みんな戦争のために絵を描くことができなくなってしまったのですから。
学校を卒業した後の10年間。そこが一番画家が伸びる時期なのではないかと、短いコレクター歴の僕でも思う時があります。画家の人生と作品を図録で振り返って見る時、やはり若い頃に充実した仕事をしている場合が多いです。その情熱と体力と研究を晩年まで通せた画家の方が稀です。
何が言いたいかというと、そんな完成された絵と比べても仕方がないということです。
ここにはそんな彼らの失われてしまった時間と、明るいはずだった未来を予感させる当時の情熱や思いが展示されていると僕は感じています。そしてそれは同時に、日本洋画史におけるこの世代の空白を浮かび上がらせ、その空白を埋められずになんとなく来てしまった現在への眼差しにも思えてくるのです。
戦後も美術会をリードし続けたのは前の世代の画家たち、つまりあの戦前パリに留学していた世代でした。もちろん、戦争から復員した画家の中にも、例えば岡本太郎や古沢岩美、池田龍雄など、たくさん素晴らしい画家がいましたが、彼らの前衛を意識した美術よりも戦前からの印象派や日本的フォーヴの方がずっと評価が高いままだったのです。
日本洋画史の前衛が見直されるようになったのはつい最近のことで、なので明らかに検証が足りていないところがあります。そのせいか僕たちの世代、いやそのもっと前の世代から日本洋画史とは関係のないフィールドで美術をせざるを得ない状況になっているように見えます。これは戦争によって失われた世代があったこと、またそこから目をそらし続けたことが要因にあると僕は思っています。
今一度、この図録の絵を見ると、彼らがどんな絵を描く画家になっただろうと想像しないわけにはいきません。きっと、素晴らしい画家になることができた人もいたと思います。
そうでなくとも、僕の集める物故画家のように終生絵筆を持ってキャンバスに向かっていたことでしょう。
そんなささやかな機会すらあっという間に奪っていったそんな時代があったことを、またそんな人たちが同時に加害者として銃を構えなければならなかったことを思いながら、自分に何ができるのかを今日も考え続けています。
皆様も是非、図録だけでもお手に取ってみてください。
ではでは、また。
下記二冊も副読本としておすすめです!